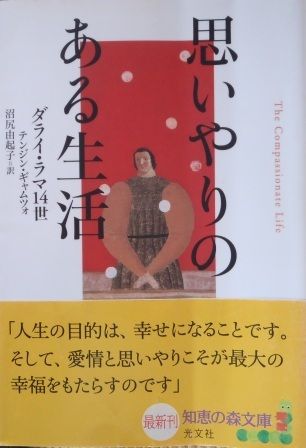 2006年刊行。
2006年刊行。
この本の帯にある
人生の目的は、幸せになることです。そして、愛情と思いやりこそが最大の幸福をもたらすのです
というセリフを、日本にあまた犇めくスピリチュアルカウンセラーが言ったとしたら、そうしたポエティックな物言いが好きな女&子ども&オネエ以外の誰も立ち止まりはしないだろう。
さらに、
思いやりや忍耐は立派な志だと考えているだけでは、育むのに十分ではありません。困難なことが起こるのを待って、それから思いやりなどを実践してみるのです。
では、誰がこのようなチャンスをつくってくれるでしょうか。
それはもちろん、友人ではなく自分の敵です。
最も厄介な目にあわせるのが敵ですから、心から学びたいと願うのであれば、敵を最良の教師と見なそうではありませんか! 思いやりや愛情を大切にしている人にとって、忍耐の実践は必須のものなので、敵対者は必要欠くべからざる人というわけです。穏やかな心持ちを育むのに一番手を貸すことができるのは敵です。わが敵をありがたく思う必要がありそうですね!
という発言を、日本の政治家や宗教者が口にしたときに、思わず鼻でせせら笑うか、眉を顰めるか、ケツを痒きたくなるか、しない者がいるだろうか。(某元首相の「友愛」発言を思い出してほしい。)
「こんな子どもっぽい理想論=絵空事を言う大人は信用まかりならん。どうせなにか下心か算段があるんだろう。でなければ、現実を知らないお坊ちゃまなんだろう。」
と思うのではないか。
しかし、これらの発言をしたのがダライ・ラマ14世だとなると、話は違ってくる。
彼と彼が君主である国チベットは、中国という現実の残忍にして強大な敵を持ち、現実の侵略と圧政がもう何十年も続いていて、現実に殺されているチベット人が百万人を超えているのである。ダライ・ラマ14世の経験した苦難は現実のものであり、祖国を奪われ同胞を殺された悲しみは想像を絶するものであり、世界の誰一人も彼ほどの忍耐と寛容を要求されてはいまい。通常なら、彼の立場にいる君主が中国に対して抱くであろう怒りと憎悪は、原子爆弾数発を広い中国大陸のあちこちに投擲しても収まらないくらい、すさまじいものと想像する。
その彼が、本気で上記のような発言をするのだから、襟を正して読まずにはいられまい。
以下、引用。
●結局のところ、人間は社会的な動物です。人の友情や人の笑顔がなければ、人生はみじめになり、孤独はやがて耐え難いものになります。
このような人間の相互依存性は、「自然法則」です。つまり、自然界の法則や人間の社会原則に従って、他者に依存しながら人は生きていくのです。
●自分自身の利益や願望はどのように実現されるのでしょうか。仏教の考えでは、自己の利益や願いは生きとし生けるもののために働いた副産物として満たされます。
●思いやりと愛着の違いを明らかにしてみましょう。愛着と違って、本物の思いやりは、たんなる感情的応答ではありません。まことの思いやりとは、根拠のある堅固な係わり合いです。
このしっかりした土台があるからこそ、他者に対する思いやりのある心構えは、たとえ相手が否定的に振る舞っても変化することはまったくありません。正真正銘の思いやりとは、自分自身の主観や期待に基づいているのではなく、むしろ他者のニーズに基づいています。相手が親友であっても敵であっても関係なく、平安や幸福を願い、苦難に打ち勝ちたいと望む。そう思う限り、この切望を基盤として私たちは問題と真に係わり合えるようになります。
●他の人が自分とは異なるイデオロギーや宗教上の意見を持っている場合、相手の権利を尊重し、思いやりのある態度を示せば、その人の考えが自分に相応しいものであるかどうかは問題ではなくなり、意見の相違は二次的なものになります。その人が持論を信じ、それから恩恵を得ている限り、当の人物の純然たる権利です。
●宗教が生活に欠くことのできない一部となったときに初めて、宗教は効力を発揮します。
●仏教の教えでは、苦しみの消滅を幸福の最高の状態と表現しています。この幸福を愉快で楽しい感覚に置き換えてはなりません。仏教徒は感覚や感情のレベルで幸福を語っているのではなく、むしろ、幸福の最高のレベル、すなわち苦しみと迷いからの完全なる解放に言及しています。
まったく、驚くべき人間性の陶冶というほかない。
それを可能にしてくれるのが仏教なのである。
最後に、著者が紹介する十二世紀の師ラングリ・タンパの著『心を鍛錬する八篇の詩』より
否定的な性分の人や
苦痛が重くのしかかっている人に出会えば
宝物を発見したかのように尊きものと見なさんことを
遭遇することは稀有であるがゆえに