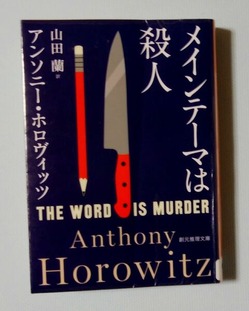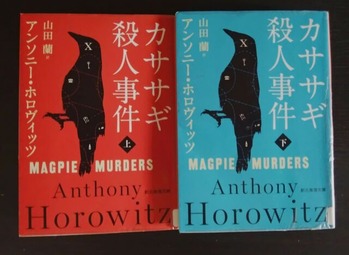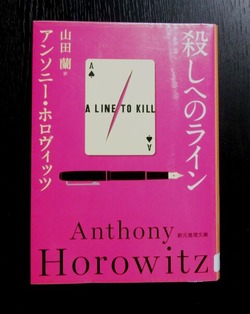2011年原著刊行
2013年(株)KADOKAWAより邦訳発行
2015年文庫化
2015年文庫化
名探偵ホームズのパスティーシュ。
著者はむろん、アーサー・コナン・ドイルではなく、1955年生まれロンドン在住の作家である。
パスティーシュ(仏: pastiche)は、作風の模倣のこと。音楽・美術・文学などにおいて、先行する作品の要素を模倣したり、寄せ集め、混成すること。(ウィキペディア「パスティーシュ」より抜粋)
ホームズものを完読しているシャーロキアンたちは、もはや新作が読めない悲しさを才能ある作家のパスティーシュによってかろうじて慰めることができる。
ホロヴィッツの才能はなかなかのもので、ホームズとワトスンのキャラクター造形が原作に忠実で、「こんなのホームズじゃない!」「ワトスンはこんな馬鹿(あるいは利口)じゃない!」といった苛立ちをまったく感じさせなかったばかりでなく、ミステリーとしても上出来である。平行して起こる二つの異様な事件をうまく組み合わせて、ホームズを牢獄に送り込みそこから鮮やかに脱走させるといったスリル満点のプロットを紡ぎだし、意外な犯人や衝撃の結末にも事欠かない。
シャーロキアンにはおなじみの愛すべき人物たち――ハドスン夫人、レストレイド警部、ワトスン夫人、ホームズの兄マイクロフト、ベイカー街浮浪少年団、そして宿敵モリアーティ教授!――を登場させて読者を喜ばせてくれる。ソルティは殊に、弟を凌駕する天才的頭脳を持ちながら孤独と怠惰を愛するおデブさん、イギリス国家の影のフィクサーたるマイクロフトが好きである。
また、ロンドンの下町やスラムの情景が眼前に浮かんでくる文章は、さすがロンドンっ子の面目躍如である。
また、ロンドンの下町やスラムの情景が眼前に浮かんでくる文章は、さすがロンドンっ子の面目躍如である。
ホームズものとしては、絶対にドイルが書かないようなショッキングな真相が待っている。
思い返してみたら、ホームズものにはセックスに関わるエピソードが排除されている。時代の制約というものだろう。
当時イギリスはヴィクトリア女王が君臨していた(在位1837~1901年)が、ヴィクトリア朝的という用語には、「非常に厳しいがしばしば偽善的な道徳的基準」といった意味合いがあるそうだ。
抑圧すればするほど変態度を増していくのがセックスというものである。
思い返してみたら、ホームズものにはセックスに関わるエピソードが排除されている。時代の制約というものだろう。
当時イギリスはヴィクトリア女王が君臨していた(在位1837~1901年)が、ヴィクトリア朝的という用語には、「非常に厳しいがしばしば偽善的な道徳的基準」といった意味合いがあるそうだ。
抑圧すればするほど変態度を増していくのがセックスというものである。
評価: ★★★
★★★★ 面白い! お見事! 一食抜いても
★★★ 読んでよかった、観てよかった、聴いてよかった
★★ いい退屈しのぎになった
★ 読み損、観て損、聴き損